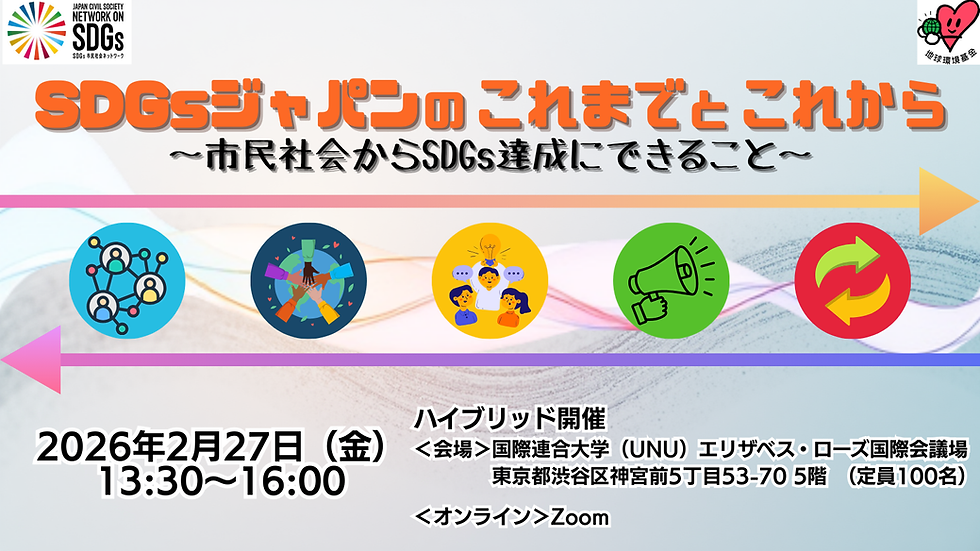[参加報告]JACSESセミナー「気候変動・気候危機に対処するための施策・ファイナンス・情報基盤」
- sdgsjapan

- 2021年2月14日
- 読了時間: 3分

2月3日に、環境ユニット幹事団体であるNPO法人「環境・持続社会」研究センター(JACSES)が主催したセミナー「気候変動・気候危機に対処するための施策・ファイナンス・情報基盤 ~国会『気候非常事態宣言』決議を受けて~第1回:被害を回避するための世界の温室効果ガス削減と日本」に参加しました。
(報告:SDGsジャパン ボランティア 大沼優)
主催:JACSES
講師:
足立治郎氏(JACSES事務局長)
大髙準一郎(外務省国際協力局気候変動課長)
田辺清人氏(地球環境戦略研究機関上席研究員 兼 IPCCインベントリータスクフォース共同議長)
小野洋(環境省地球環境局長)
遠藤理紗氏(JACSES気候変動プログラムリーダー)
イベント詳細:http://jacses.org/853/
イベントでは、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響が生じる前から喫緊の課題とされている、SDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」を中心に意見が交わされました。
小野氏から、脱炭素社会に向けた世界の動きを始め、途上国支援の「脱炭素移行のための一貫体制の構築」や、「環境インフラ海外展開プラットフォーム」の仕組みをご紹介いただきました。各現場のニーズに沿った支援が重要であるとお話がありました。
大髙氏からは、「気候変動に関する国際枠組み」の変遷や、主要国の具体的な取り組みについてご説明がありました。気候変動の課題にこれまでになく注目が集まっており、コロナ復興の中でCO2を排出しない産業転換が必要とされていること、また、世界共通の脅威となっているCOVID-19への対応で世界や人々の結束が求められている点が強調されました。
田辺氏は、先進国と途上国での温室効果ガス排出に関する定義の違いや、実際の排出量の状況、「パリ協定」が示す目標の達成への道筋について話されました。温室効果ガスには二酸化炭素以外のガスも含まれており、それらのガスの排出実態にも注目すべきだと話されました。
遠藤氏は、気候危機への対処法や日本にできる貢献についてご提案されました。「気候変動」ではなく「気候危機」に突入してしまっている現在に、国内のみならず海外を含めて日本は何ができるのか、SDGsの目標17も合わせて解決への道を検討する視点が示されました。
SDGゴール13では「気候変動に具体的な対策を」と明示されていますが、「気候危機」であるという現状を一人ひとりがきちんと理解しなければならないと思いました。一国だけが取り組む課題ではなく、国々が連携し、地球規模で取り組んでいかねばならない課題であると再認識しました。また、SDGsのどれか1つの目標に取り組むにあたり、他の目標へのポジティブな影響やネガティブな影響を踏まえることも重要な視点です。
「気候危機」は、自然由来ではなく、人間が過度に便利な生活を求めた代償によって引き起こされたと言えます。その状況は私たちの対策の遅れもあり、悪化の一途を辿っています。これから先に明るい未来が開けるように、今やらなければならない取り組みについて各セクターとともに始める必要があると感じました。