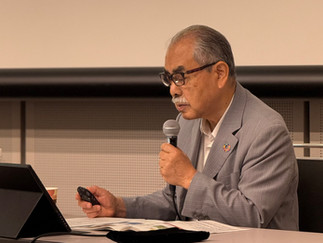<報告>「協同組合フェスティバル」に企画協力、「“協同”がより良い世界を築く~連続シンポジウム・座談会 第4回SDGsと協同組合」に登壇
- 2025年7月7日
- 読了時間: 5分
2025年7月5日(土)、東京国際フォーラムにて、2025国際協同組合年実行委員会(事務局:日本協同組合連携機構(以下、JCA))主催の「協同組合フェスティバル」が開催されました。SDGs市民社会ネットワーク(以下、SDGsジャパン)は、2025国際協同組合年実行委員会の実行委員団体です。
毎年7月第1土曜日は全世界において国際協同組合デーとされており、記念イベントとして実施された「協同組合フェスティバル(約4,000人が来場)」において、同会場での「SDGsスタンプラリー」に、企画協力しました。
また、同会場Dホールからハイブリッド形式で開催された「“協同”がより良い世界を築く~連続シンポジウム・座談会」第4回「SDGsと協同組合」も、企画協力し、共同代表理事大橋正明、理事星野智子、事務局長新田英理子がそれぞれ、登壇しましたので、以下、概要を報告します。
第1部:SDGsと協同組合
〜実践状況、達成への課題と期待〜
第1部には、SDGsジャパン 大橋正明の他、比嘉政浩さん(JCA 代表専務理事)、村木厚子さん(全国社会福祉協議会 会長)、落合航一郎さん(慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士2年)が登壇され、コーディネーターをSDGsジャパンの新田英理子が務めました。
冒頭では、JCA 比嘉代表専務理事より、協同組合によるSDGsへの貢献が進んでいる一方で、認知度や発信に課題があるとの指摘がありました。2025年が「国際協同組合年」にあたることを踏まえ、取り組みの可視化や社会への発信を一層強化していく必要性が語られました。
続いて、各登壇者からは、日本および世界におけるSDGsの進捗状況、協同組合・市民社会が果たす役割、理念と現実のギャップをどう乗り越えるかといった視点、さらには地域共生や福祉の再構築に向けた具体的な提案が共有されました。また、日本生活協同組合連合会 サステナビリティ推進グループの新良貴泰夫さんより、生協におけるSDGsの取り組み事例も紹介されました。
パネルディスカッションでは、「SDGs達成期限まで残り5年6か月となる中、どのように個別の実践を連携させていくのか」をテーマとして議論を進めましたが、登壇の皆さんからは、「〇〇すべきという、理念や理想だけでは進まず、”好き”が大事である。そしてそれを社会課題とのつながりを見いだしていくと行動のきっかけになるのではないか」という視点や「連携のためには、SDGs推進円卓会議の経験からも、市民社会組織が持っている当事者の視点。当事者の話しをじっくりと聞く姿勢の重要性」や、「日本の科学技術イノベーションシステムの対OECD比較の調査から、他社とつながることが苦手であるという調査結果が出ている中での協同組合のつながる力の可能性」について等、具体的な視点が共有され、活発な意見交換が行われました。
さらに、「すべてを一人で担うのではなく、できることを持ち寄り連携することで、より大きな力が生まれる」といった、協働の意義と可能性についても改めて確認されました。
第2部:持続可能な暮らしのために、先人から学び、未来へ繋ぐ
〜協同組合の父 賀川豊彦とSDGs〜
第2部には、石部公男さん(賀川豊彦記念松沢資料館館長)、斉藤弥生さん(大阪大学大学院人間科学研究科 教授)、伊藤由理子さん(生活クラブ事業連合生活協同組合連合会 顧問)が登壇され、SDGsジャパン理事の星野智子がコーディネーターを務めました。日本の協同組合運動の先駆者・賀川豊彦の実践と、北欧の福祉社会における自治と協同のあり方を通じて、持続可能な社会に向けたヒントが探られました。
賀川豊彦は、貧困や災害支援に取り組む中で協同組合を社会運動として展開し、1920-1930年代のデンマークやスウェーデンを視察。当時から福祉国家としての基盤を築き始めていた北欧社会の仕組みに注目し、その理念を日本に紹介しました。
松沢資料館 石部館長から、賀川豊彦はSDGsが採択される100年以上も前から貧困や子どもの権利など、現在のSDGsに通じる取り組みを実践的に行っていたことが紹介され、大阪大学 斉藤教授からは、北欧に根付いている、自治体が社会サービスの提供責任を担い、住民が税を納めて政策に関わる「参加型の福祉社会」と、賀川豊彦が見た北欧が紹介されました。生活クラブの伊藤顧問からは、実際にデンマークを視察した経験に学びつつ、FEC(食・エネルギー・ケア)自給やローカルSDGsといった地域での実践へとつなげている事例が紹介されました。
パネルディスカッションでは、「協同組合は社会の助け合い運動の基礎」であり、「競争ではなく連携」を前提とした経済・福祉のあり方が求められているとの意見が交わされました。日本の実践が北欧の研究者にも注目されていることから、国際的な「学び合い」の重要性も強調されました。
こうした議論を受けて、会場からは「自然災害と協同組合の関係」についての問いかけも寄せられ、登壇者からは、災害時に発揮される「助け合い」の力を、平時から暮らしや地域の中に根づかせていく重要性が語られました。また、非常時には地域内だけでなく、他の地域との連携による「広域的な助け合い」も不可欠であるとの指摘もありました。こうした「協同」の理念によってこそ、人びとが尊厳を持って自立し、安心して暮らす社会が築かれるとの視点も共有され、協同組合の果たすべき役割があらためて確認されました。
------
本シンポジウムでは、協同組合の実践と理念を起点に、SDGs達成に向けた現状や課題を多角的に見つめ直すとともに、過去の経験や他国の取り組みに学びながら、持続可能な未来を築くための知見と連携の可能性が語られました。
SDGsジャパンは、希望をつなぎ、危機の克服をあきらめることなく、協同組合をはじめとする多様なステークホルダーと手を携えながら、残された5年半の道のりを共に歩み、SDGsの達成に向けて取り組んでまいります。
(松野有希/政策提言・事業コーディネーター)